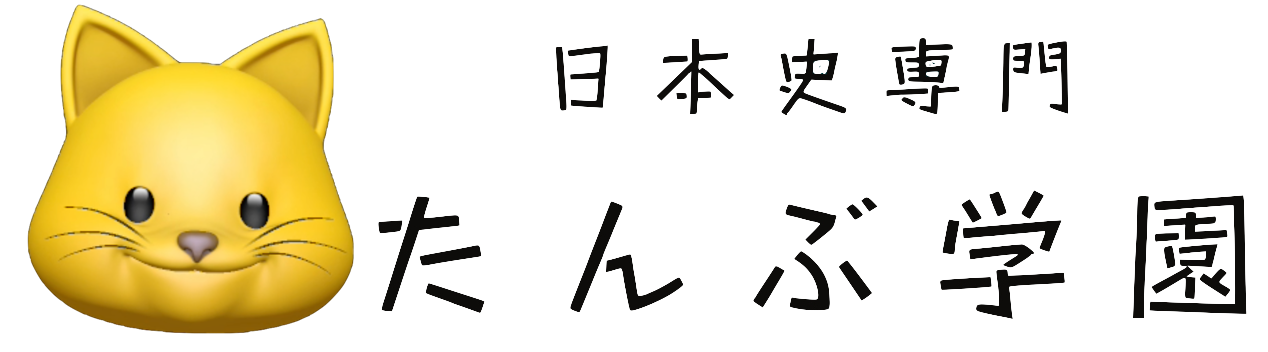【3分日本史】摂関家の他氏排斥
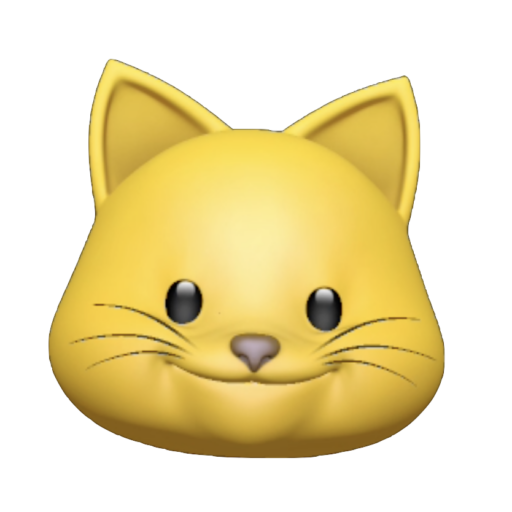
今日は摂関家の他氏排斥について勉強しましょう
| 天皇 | 摂関家(北家) | 政変 | 役職 | 処罰された人・関係者 | 備考 |
| 嵯峨 | 冬嗣 | 薬子の変(810) | 藤原薬子・仲成(藤原式家) | 式家没落、北家が台頭 | |
| 仁明 | 良房 | 承和の変(842) | 橘逸勢・伴健岑 | ||
| 清和 | 〃 | 応天門の変(866) | 人臣初の 摂政(858) | 伴善男(大納言) | |
| 宇多 | 基経 | 阿衡の紛議(887) | 初の 関白(887) | 橘広相 | |
| 醍醐 | 時平 └摂関になっていない | 昌泰の変(901) | 菅原道真(太宰権帥へ) | 時平の死後摂関を置かず →延喜の治 | |
| 村上 | →天暦の地 | ||||
| 円融 | 実頼 | 安和の変(969) | この変以降 摂関が常置に | 源高明(醍醐天皇の皇子) |
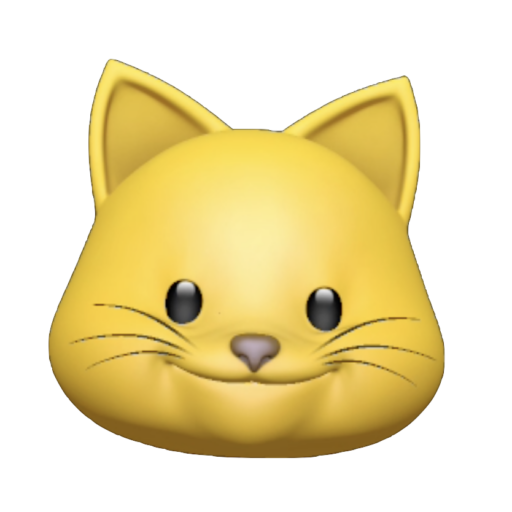
摂関家の他氏排斥です。
まずは語呂合わせで覚えましょう
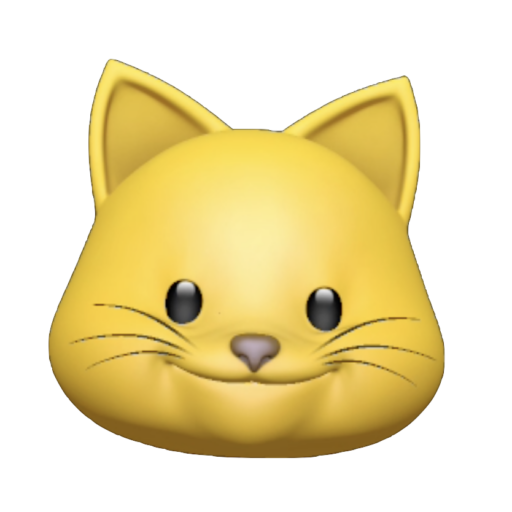
まずは薬子の変です。
これは「他氏」ではなく藤原氏の中の式家です。
平城京にいた平城太上天皇が復位・復都を狙って起こしたクーデターです。
平城太上天皇に寵愛を受けていた藤原薬子と、
その兄の仲成が太上天皇をけしかけたとして処罰されます。
薬子は服毒自殺、仲成は射殺(弓矢で)されます。
これで奈良時代、摂関家の中心的な活躍をしていた式家は没落していきます。
ちなみに平安京ではこの後保元の乱まで死刑はありませんでした。
薬子と平城太上天皇の関係はなかなかタダならぬものがあるので、
よかったら下も読んでくださいね
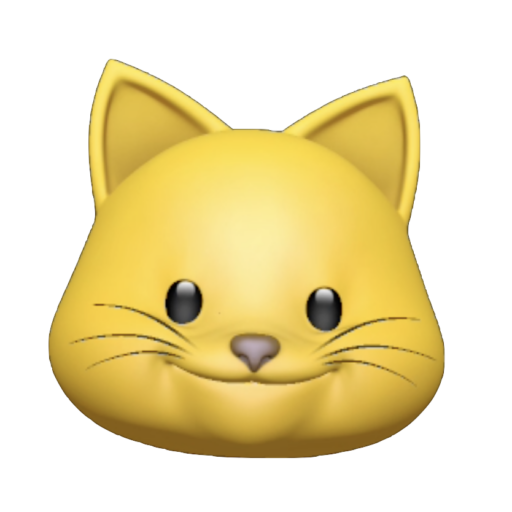
承和の変です。
古代からの名族である伴健岑と橘逸勢が失脚させられた事件です。
これは仁明天皇が自分の皇子・道康親王(のちの文徳天皇)を皇太子につけようとして、
当時の皇太子(恒貞親王)を廃位した事件です。
そしてこの道康親王の母親は藤原良房の妹です。
有力貴族のバックがない恒貞親王の後見人であった嵯峨上皇が亡くなりました。
その2日後に
「伴健岑と橘逸勢が恒貞親王と謀反を企てている」
として捕らえられます。
そして恒貞親王は廃太子され、道康親王が皇太子となります。
この時中納言だった藤原良房は大納言となって、順調に出世していきます。
橘逸勢は三筆の一人でもありましたね。
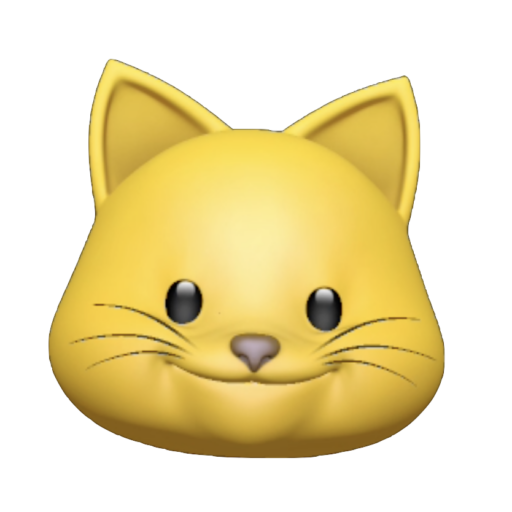
次は応天門の変です。
応天門に放火した伴善男が失脚した事件です。
まず、大納言であった伴善男と
左大臣であった源信(みなもとのまこと)は政敵でした。
866年に伴善男は源信の失脚をねらい、
源信の仕業だと思わせるようにして、応天門に火をつけました。
事件の後、伴善男は「源信が応天門に放火をした」と密告します。
しかし、良房が源信の弁護をしたことにより、源信は無罪とされました。
ところで・・・
伴善男の家来の子どもが他の子と喧嘩をしていました。
そこに親である善男の家来がやってきて、
相手の子をボコしました。
相手の子の親は怒り、
「伴善男が応天門に火を付けた」
ということをばらしてしまいました。
これを機に、伴善男など数名の首謀者の取り調べが行われ、
伴善男は犯行を認める自白を行い、
伊豆国に流罪としました。
そのほか紀豊城も安房国に流されました。
有力官人であった伴氏、紀氏ともに失脚することとなってしまいました。
この処分後、源信と藤原良相の左右の大臣が相次いで急死し、
朝廷の全権力が良房のもとに集中することとなりました。
ついに、866年に
良房は臣下として初めて摂政(清和天皇の)の職に就任
することとなりました。
応天門の変は
「伴大納言絵巻」
という絵巻物になっていることでも有名です。
「伴大納言絵巻」も頻出ですので、
ちょっと長くなりましたが、ことの経緯を書いてみました。
先の承和の変もそうですが、
伴氏、紀氏といった古来からの名族が狙われているのは明白ですね。
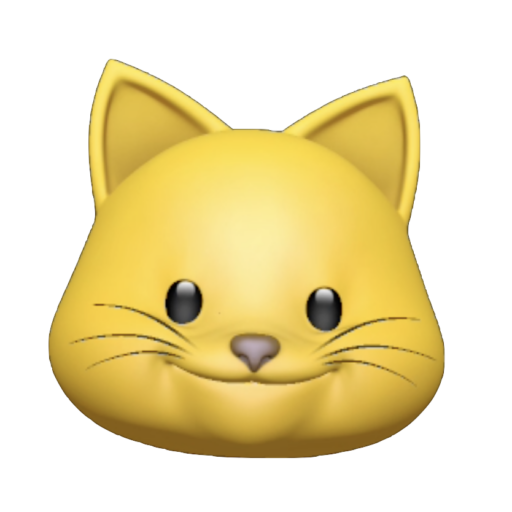
つぎは阿衡の紛議です。
これは関白に任ぜられた藤原基経がその役職の内容に不満でゴネた・・・
その責任をとらされて橘広相が処罰された・・・
という事件です。
「関白」は基経の時にできた新しい官職です。
なのでまだその地位が確立していない時期に
「関白ってのは中国の阿衡みたいなもんです」
って宇多天皇が橘広相に書かせたわけです。
ところが
「阿衡というのは地位は高いが職務を持たない」
とチクるやつがいて
チクられた基経が相当ゴネて、1年間一切の政務に関わりませんでした。
結局、宇多天皇は橘広相を罷免しますが、基経の怒りが収まりません。
そこに現れたのが菅原道真です。
彼が基経に
「これ以上ゴネると藤原氏のためによくないんじゃね?」
という手紙を送り、基経も落とし所とします。
これで関白の地位と権力が決まったという出来事です。
このゴネ得事件の背景には
橘広相の娘が宇多天皇の妃の一人で、
彼女の生んだ子が即位したら藤原氏に打撃なので
イチャモンをつけて失脚させた、
という一面があります。
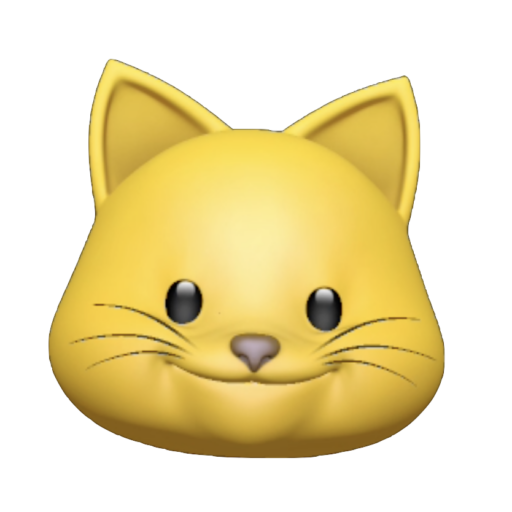
次は昌泰の変です。
右大臣・菅原道真が大宰権帥として太宰府に左遷させられた事件です。
阿衡の紛議で藤原氏のアクの強さに辟易した宇多天皇は
学者の菅原道真を登用します。
実は菅原道真は阿衡の紛議でも少し絡んでいます。
その時讃岐守だった菅原道真は任地から帰京し、
橘広相を罰しないように意見書を出しています。
阿衡の紛議の当事者である藤原基経は
菅原道真の能力を認めていたようで
学者からの意見ということもあって基経は矛を納めています。
基経の死後、側近だった橘広相も亡くなり、
宇多天皇は自分の側近に
菅原道真を置きます。
この菅原道真という人は、
かなり同僚たちから色々と言われていた節があります。
上記の讃岐守への転勤前、道真は文章博士という地位にいました。
今で言えば東大の学長みたいなもんでしょうか。
讃岐の国司へ決まった時の送別会で藤原基経から
「ちょっと詩を詠んでや」と頼まれても
あまりの悲しみに嗚咽が止まらず一言しか言えなかったようです。
道真が文章博士になった時に父は
「文章博士は妬まれやすいから気をつけや」
と言われたようですが、色々と妬まれ話があります。
しかし、一説には道真が真面目すぎて
息苦しさを感じていた貴族も多かったとか。
秀才の名高い道真からすれば、他人のアラが目につくのでしょうが
それをいちいち追求されていてはたまらないものです。
自然と道真を宮中から追い出そうという空気ができてきたようで
彼は何度か左遷の危機にあります。
上記の讃岐の左遷もその一つかもしれません。
また894年、遣唐大使として唐に派遣されそうになりますが
「唐は滅びそうなので得るものはない」という建議で派遣は実施されず、
907年の唐の滅亡を持って遣唐使の歴史も終わります。
道真の娘の一人が宇多天皇の皇子の妃となります。
やがて宇多天皇が退位し、醍醐天皇に譲位します。
道真も宇多上皇の側近として右大臣にまで出世します。
ところが「道真が醍醐天皇を廃位し、娘婿を即位させようとしている」
という噂が流れ、道真は太宰権帥として左遷されます。
これは政務に携わることが許されず、衣食住もままならない、
左遷というよりはほぼ流刑、間接的な死刑といえ、道真は憤死します。
道真は死後、怨霊になったと言われます。
政敵・藤原時平などが亡くなったのはそのせいとされています。
また宮中にも落雷があり清涼殿を直撃し多数の死傷者を出した事件も
道真の怨霊の仕業とされました。
この様子を見た醍醐天皇も3ヶ月後に亡くなります。
その後、道真は雷の神様・天神として北野天満宮に
祀られるようになりました。
そして全国の天神、天満宮が菅原道真を祀るようになり
道真の学力にあやかり、学問の神様として人々の尊崇を
集めるようになりました。
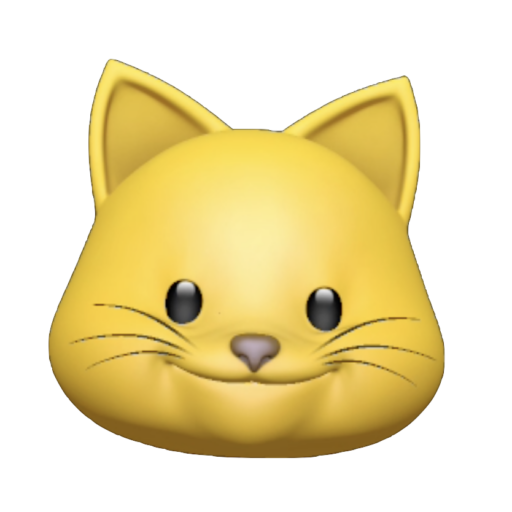
最後は安和の変です。
源満仲の讒言で左大臣・源高明が左遷された事件ですね。
時の天皇、冷泉天皇(関白が藤原実頼だが外戚関係にはない)に
子がまだ無い時、為平親王と守平親王のどちらかを
立太子することになりました。
年長者の為平親王が立太子されると思われましたが、
藤原氏と関係のある守平親王(のちの円融天皇)が
立太子されました。
為平親王は源高明の娘婿だったんですね。
この2年後に源満仲(源経基の息子)らから「謀反を企んでる」と密告がありました。
謀反の中身はよく伝わっていないのですが、
為平親王を擁立しようとしてんじゃないの?
と疑われ、源高明ら関係者が左遷、流罪となりました。
(源高明は太宰権帥へ)
この事件以降、摂政・関白が常置される事になります。
ここで「源氏が源氏を売るってどういうこと?」
となるかもしれませんが、
源高明は醍醐天皇の皇子なので醍醐源氏
源満仲は清和天皇の流れなので清和源氏です。
皇族から外れて姓を与えられる時は
源や平、橘を与えられます。
なので同じ姓でも違うということが起きるのです。
余談ですが、この時の天皇、冷泉天皇は奇行が多かったと伝えられる天皇です。
足が傷つくのも全く構わず、一日中蹴鞠(リフティングみたいな遊び)を続けたとか、
幼い頃、父の村上天皇に手紙の返事として、男性器が大きく描かれた絵を送りつけたとか
清涼殿近くの番小屋の屋根の上に座り込んだとか
病気で床に伏していた時、大声で歌っていたとか
退位後に住んでいた御所が火事になった折、避難するときに牛車の中で大声で歌ったとか
今で言えば発達障害だったのか、
それとも藤原氏から身を守るためにわざとやったのかわかりません。
ただ大変な男前だったそうで、和歌の才能もあったとか。